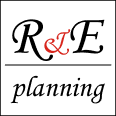私が住宅会社に勤めていた当時、「高断熱高気密住宅」の新たな工法を開発するプロジェクトが立ち上がりました。開発のヒントを求め、国内でも高断熱高気密の先進地域とされる岩手県へ視察に出かけたときのことです。
訪れたのは、雫石近くにある地元放送局が主催する住宅展示場。そこに建てられていたモデル住宅はすべてが「高断熱高気密住宅」仕様でした。暖房方式は、ルームヒーター、床暖房、薪ストーブ、パネルヒータ、エアコンなど多様で、各社が工夫を凝らしている様子がうかがえます。
展示場を見学して感じたことをいくつか挙げてみます。
【快適なはずの高断熱高気密住宅で感じた“違和感】
- 室内はやや暑く感じる空間が多く、暖房機器に触ると「火傷するのでは」と思うほど高温でした。
- 部屋ごとに温度差があり、特に吹き抜け階段の途中で寒暖差を強く感じたモデルも。
- 熱がこもっているような閉塞感があり、“快適”とは言いがたい空間もありました。
【本当に快適だと感じた住宅も】
その一方で、家全体が22〜23℃で安定しており、温度差を感じない快適なモデル住宅もありました。空気が穏やかに循環し、「自然体で過ごせる住まい」と感じさせてくれたのです。
【質問への対応から感じた“技術理解の深さ】
高断熱高気密の仕様や換気、暖房の仕組みについて質問を重ねたところ、しっかりと答えてくれる住宅会社もあれば、うまく説明できない担当者もいたのが印象的でした。
同じ「高断熱高気密住宅」と銘打っていても、住まいの快適性には「質の差」があります。
ただ断熱・気密性能が高ければいい、というものではなく、暖房・換気・空気の流れや室温のコントロールまで含めて「住まいの性能」だと実感しました。
この視察は、私たちが目指す本当に快適で、省エネにも優れた住宅づくりの原点になりました。
雪深い岩手の冬。マイクロバスに揺られながら、今晩の宿へ向かう道中、私は「性能を語るだけではなく、体感で伝える家づくり」の大切さを噛み締めていました。
次回は、宿泊先での暖房体験についてお伝えします。